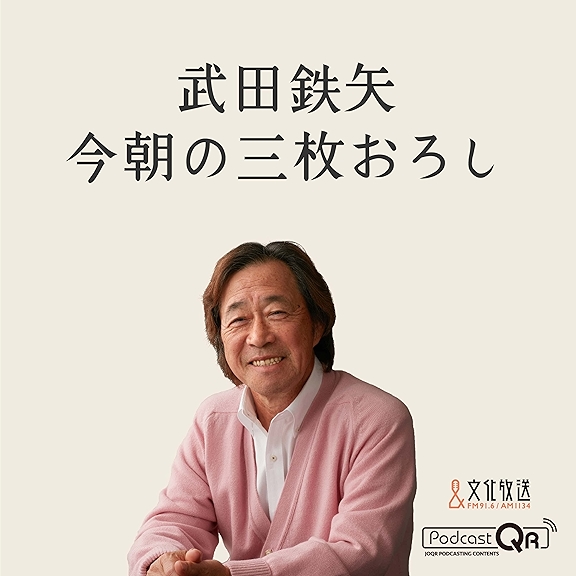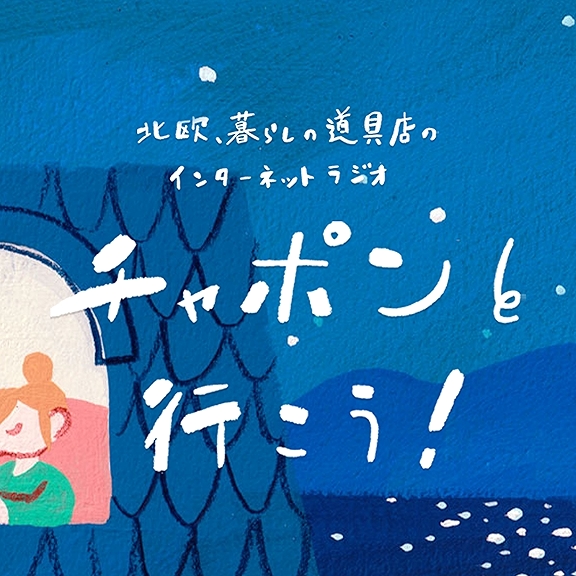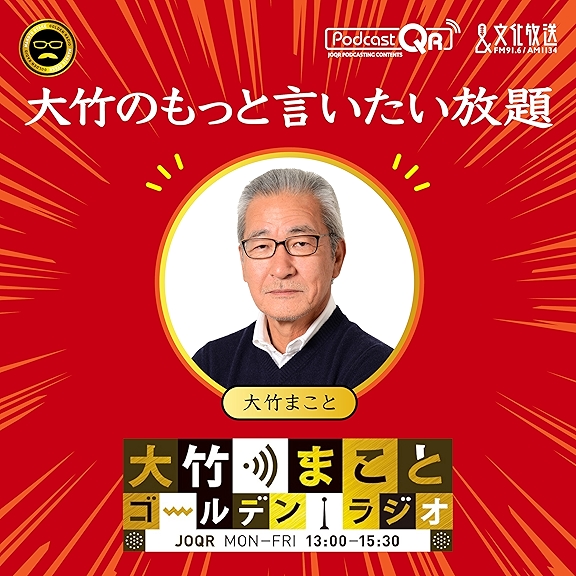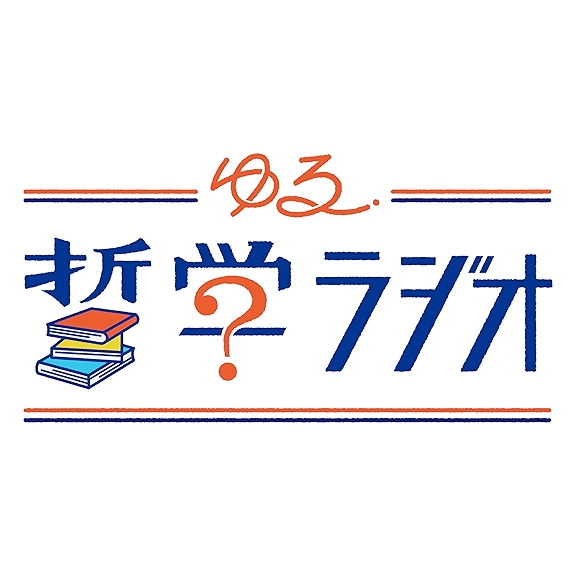#40 みんまちトーク『住宅地&団地のまちづくり(2);「みんまちノート」連動型対談』
この番組は「認定NPO法人日本都市計画家協会;通称JSURP(じぇいさーぷ)」がお届けするポッドキャスト『みんなのまちづくりトーク』です。毎回多彩なゲストと共に、いま話題のまちづくり事例、新しい制度、活動のhow-toなどを紹介していきます。
★☆★「この番組、いいね♪」とお感じになった方は是非、当協会(JSURP)へのご寄付を御願いします!あなたのご寄付がわたしたちNPO法人のエネルギー源になります!https://jsurp.jp/nyuukai/
第40回は、前回に引き続き、当会Jsurp日本都市計画家協会の常務理事中川智之(なかがわさとし)と理事・副会長高鍋剛が住宅地のまちづくり、団地再生について語り合うシリーズの第二回です。当会オリジナル『みんなのまちづくりノート』の「vol.2 住宅地のマネジメント」と「vol.11 団地再生のまちづくり」に沿いながらお話しする番組となっていますので、是非当会Webサイトから各ノートをダウンロードしたうえでご視聴をお楽しみ下さい。
▼話していたことのリンク
Jsurp日本都市計画家協会オリジナル『みんなのまちづくりノート』
https://jsurp.jp/gyouseki/
(vol.2 住宅地のマネジメント、vol.11 団地再生のまちづくり)
株式会社アルテップ
http://www.artep.co.jp/
小山田桜台団地のまちづくり
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/danti-reclamation/oyamadasakuradaidanchi.html
めじろ台地区まちづくり協議会
https://new.mejirodai.tokyo/
▼出演者
◆中川 智之(なかがわ さとし)氏;1959年大阪府生まれ。東京理科大学工学部建築学科卒業、同大学院修士課程修了。株式会社アルテップ代表取締役、認定NPO法人日本都市計画家協会常務理事。技術士(都市及び地方計画)、一級建築士。著書に「景観法を活かす」(共著、学芸出版社)、「まちづくりのための建築基準法集団規定の運用と解釈」(共著、学芸出版社)、「環境貢献都市-東京のリ・デザイン」(共著、清文社)、「マンション建替え-老朽化にどう備えるか」(共著、日本評論社)など。
□パーソナリティ:高鍋剛(Jsurp理事・副会長)
◇フリーBGM・音楽素材MusMus https://musmus.main.jp
▼キーワード
ハードの老朽化やバリアフリー非対応、買い物の支障など確かに課題は多い/一方で高齢者と言っても大半は元気な団塊の世代/経歴も多種多様で豊か/ポジティブな面が見えてくる/みなさんの知恵を活かしたまちづくりは案外面白い/比較的みなさん時間がとれることも多い/ VOL.11-P7-8;小山田桜台団地の場合、45%超の高齢化だが子育て層もいる団地/センター内の空き店舗を活用するきっかけで議論だけでなく実践することを通して、参加するひとたちの意識が変わっていった/具体的には空き店舗を自由に集える居場所にして/持ち寄り型の図書スペースやこども食堂などに/高齢者のひとたちも交流/そのような活動をする際に心配なのはお金だがその点はどうしたか/一店舗の改修でも4-500万円はかかってしまう/助成金を狙う方法もあるがこのケースでは出来なかった/この場合は700万円ほどの初期投資を自分たちでなんとか賄った/一方で運営費も課題になるがなんとかみんなのチカラでやりくりしている/共感の輪をどれだけ広げるかという点も重要/八王子市のめじろ台でもいろんなテーマで活動/駅前商店街の空き店舗を居場所にした/寄付を募ったが資金調達としてというより関心を呼び込む手段と考えた/クラウドファンドは運営が大変そうだったので諦めた/賃料を安くして貰い本棚オーナー制度などでなんとか運営できた/目白台の場合は銀行から資金調達するために一般社団法人にしたが小山田桜台団地の場合は任意組織/議論が進むにつれ組織の在り方もテーマになる/地域に庭の花が立派なお宅がありオープンガーデンの日をつくったり/座る場所が少ない(小さな公園が少ない)ので「みんなの椅子プロジェクト」として不要になった椅子を集めて置かせて貰える場所に置くという取り組みも/小さな取り組みが沢山増えている/郊外の団地には(実は)地域資源が多い/いかにみつけて活かすかという点が重要/地域資源の例として小山田桜台団地の場合、緑は多いが使われなくなった公園を「冒険遊び場」として町田市が整備しており、その運営を地元で行っている/高齢者も来る人もWin-Winで楽しんでおり、良い結果になっている/70年代の団地設計は大きな公園や緑地が多く、それらをどう活かすかは鍵となる/次回は「人の問題」を取り上げる